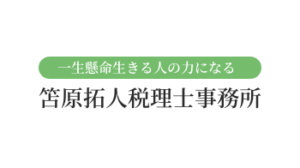「利益が出ているのに、なぜお金が残らない?」~数字に強い経営者になるための決算書活用術~
はじめに
「決算書を見ても、正直よくわからない……」「黒字なのに資金繰りが苦しい」。
これは多くの中小企業経営者から聞こえてくるリアルな声です。数字のことは税理士任せ、銀行任せになっていませんか?
しかし、経営の意思決定において「財務の数字を読み解く力」は避けて通れない力です。この記事では、財務に苦手意識のある経営者に向けて、損益計算書・貸借対照表の見方から、売上計画の立て方、手元資金を守る考え方まで、具体的に解説します。
決算書の基本構造と見るべきポイント
決算書は2枚のシートからなる
- 貸借対照表(バランスシート)
- 会社の「財政状態」を表し、ある一時点の資産・負債・純資産のバランスを見るもの。
- 損益計算書(PL)
- 会社の「経営成績」を表し、一定期間(例:1年間)の売上や費用、その結果としての利益を表す。
経営者が押さえておくべき損益計算書の利益の種類
損益計算書には「利益」が複数あります。それぞれ意味が違います。
| 利益の名称 | 意味・計算式 | 経営判断への影響 |
|---|---|---|
| 売上総利益(粗利) | 売上 − 売上原価 | 商品・サービスの利益率を測る。商売の本質が問われる |
| 営業利益 | 売上総利益 − 販売費及び一般管理費 | 会社の本業でどれだけ利益が出ているか |
| 経常利益 | 営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用 | 金融費用(利息等)を含めた日常的な損益の実態 |
| 当期純利益 | 税引前利益 − 法人税等 | 最終的に「自由に使えるお金」になる |
最も重要なのは「売上総利益」
俗に粗利益といいます。ここが儲けの源泉です。売上高ではなく、売上総利益(粗利益)です。また売上総利益は「額」だけではなく「率」も大事です。想定している売上総利益率(粗利率)になっているかは月次決算で必ず確認しなければなりません。
次に重要なのは「営業利益」
ここがマイナスですと売上総利益が少ないまたは販売費及び一般管理費(固定費)が過大であるということです。
販売費及び一般管理費(固定費)で特に注意点が人件費です。生産性を向上させて効率的にメンバーが動いていなければマネジメントの修正が必要になります。週次会議などで組織のPDCAを回していく必要があります。
また営業利益がマイナスですと経営戦略や戦術の何かを変更する必要があります。
「利益があるのにお金がない」理由とは?
このようなお悩みもよく聞きます。原因は主に以下の5つです。
借入金の返済
「損益計算書には載らないが、キャッシュが減る」ということです。借入金はお金を借りたときに損益計算書の収益にはなりません。そのため、返済したときも費用にはなりません。
売掛金の増加・回収の遅れ
特に会社が成長局面ですと売掛金が増加して運転資金がより多く必要になります。入金サイトと支払いサイトには神経質になる必要があります。金融機関からお金が借りられる財務戦略が必要になります。
在庫の過剰保有
会社が成長局面ですと在庫が増加して運転資金がより多く必要になります。また売上が下方局面でも在庫だけは積みあがるというケースもありますので、売掛金以上に注意が必要になります。
高額な設備投資
将来の収益のためなので必要な投資ですがその資金の手当方法は戦略的に行う必要があります。自己資金、借入金、リースの他に高額な設備投資であれば補助金をいただける可能性があります。
消費税の納税(預かり金の認識不足)
消費税は原則として預かった消費税から支払った消費税を控除した手元にある残額を納税する制度です。そのため、原則としては損も得もありません。ただその手元に残っているはずの残額がお金に色はついていないので運転資金に流用されてしまいます。納期限は来ていないが現在の潜在的に納税しなければならない消費税を把握して別の通帳に預金するなどが必要です。年間の消費税の納税の予測額を定期積金にするのも一つの方法です。
つまり、損益計算書では見えない“資金の動き”が、貸借対照表に表れているのです。
潰れない会社に共通する「3つの財務指標」
以下の指標は、銀行や専門家も重視する“潰れない会社”の基準です。
| 指標 | 説明 | 目安 |
|---|---|---|
| 手元流動性比率 | 月商に対して、何ヶ月分の預金を持っているか | 2ヶ月以上(できれば3ヶ月) |
| 債務償還年数 | 今の利益で借入金を何年で返せるか | 10年以内(5年未満が理想) |
| 自己資本比率 | 自己資金でどれだけ事業を賄っているか | 30%以上で「優良企業」扱い |
売上目標は「逆算」から立てよう
「とりあえず前年比105%を目指す」では、利益は出ません。
決算書を“武器”に変えるには
- 決算書を読む力は、経営の“羅針盤”
- 利益を出すことは、自己資本を増やすこと=会社の体力をつけること
- 税金を払うことは痛みではなく、未来の投資
おわりに
会計や財務に苦手意識を持つ方も多いですが、数字は「経営の言語」。読めるようになれば、社員に安心感を与え、銀行からの信頼も得られ、何より自分自身が迷わなくなります。
小さな企業だからこそ、数字に強くなりましょう。
決算書を「税理士だけが見るもの」から、「経営者の意思決定ツール」へと変えていくこと。それが、持続可能な成長の第一歩です。
名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 財務コンサルティングチーム